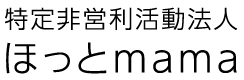コラム
公認心理師のお役立ちコラム〜障がい児の家族へのサポート〜

皆さんこんにちは!ほっとmamaで働く公認心理師のKです。
今回はシリーズ第4弾!「障がい児の家族へのサポート」について詳しく解説していきます!
◆障がい児を持つ親のストレスとその対処方法
障がいや疾患をもった子どもの親は、それが妊娠中からわかっていても、「なぜうちの子でなければならなかったのだろう」と問い続けながら、少しずつ子どもの障がいや疾患と、「障がい児の親」になった自分の人生を受け入れていきます。健診や学校での面談で、発達の遅れや行動の特性を指摘され、「そんなはずはない」と思う一方で、「他の子どもたちとは違う」という不安の間を行ったり来たりしながら子育をしている方もいます。病院で診断名を告げられたとき、「やっぱり」という思いと、「そんなはずはない」という思いが頭の中をめぐるのではないでしょうか。頭ではわかっていても、自分の子どもが「障がい児」である現実、自分が「障がい児の親」であるという現実は、とても苦しいものです。そして、そう思う背景には、自分に「差別意識」があることに気づき、それもまた、苦しい発見です。元気で明るく、やさしい子。ちょっと落ち着きがないけど、ことばが出るのが遅いけれど、「ふつうの子」と変わりないいい子・・・。自分の中に子へのイメージが崩壊し、思い描いていた子どもと目の前の我が子を比較してしまうこともあるでしょう。「この子は本当はできるのではないか」「何かを工夫すればやれるはず」「親が頑張ればできるはず」と希望を持ちたくなるときもあるでしょう発達支援の場は、子どもが安心して過ごせる場というだけでなく、ゆっくり成長するお子さんのペースに合わせて、一つ一つできることを増やしていく場でもあります。みんなと同じやり方では難しくても、工夫や時間をかければできることもたくさんあります。子どもの「できた!」は子ども本人だけでなく、親にとってもうれしいものです。保護者の苦悩や不安、戸惑いを受け止めることも、大事な役割だと思っています。
◆放課後等デイサービスが家族に与える支援と安心感
発達支援の場で、子どもがのびのびと安心してすごし、成長や発達をしている姿を見ることは、親にとても大きな救いでしょう。落ち着いて話が聴けるようになった、順番を待てるようになった、粘り強く取り組めるようになった、など昨日(過去)の我が子と比べて、成長したなぁ、できるようになったんだなぁという喜びがわいてきます。障がいや疾患があっても、子どもたちは日々成長をします。その子なりの歩みで発育・発達をするという事実は、新しい希望となるでしょう。発達支援の専門家として、保護者が子育ての希望をスタッフと語れるようになることは、子どもを中心としたチームを作ることに繋がり、安心して生活できる場(環境)を作ることに繋がるのではないかと思います。そして、子どもがのびのび、生き生きと過ごす姿は、保護者がホッと安心をし、うれしさを感じることに繋がるのだと思います。
◆家庭と放課後等デイサービスの連携を強化する方法
放課後等デイサービスなどの福祉サービスの利用を開始し始めたときに、事業者からいきなり協力を求められたり、指導や助言をされても、保護者は戸惑ってしまうことやがっかりしてしまうのではないかと思います。まずは子どもが安心できる場、自信をもって活動できる場を提供し、子どもからの信頼を得ることが大切だと思っています。子どもからの信頼を得ることで、子どもと家族の味方であると認識してもらえたら、子どものために一緒に工夫した取り組みを行うことができるのではないでしょうか。「できないと思っていたことができるようになった」という喜びを、支援者と保護者、その家族が共有できると、子ども自身も自分の成長をいろいろな場面で実感できるようになり、「できるようになること」「がんばること」の喜びや大切さを学びます。子どもが自分の成長を自分で感じて喜ぶ。それは、障がいや疾患の有無に関係のないことだと思います。子どもの日々の成長を共有することが、連携強化のポイントではないかと思います。
公認心理師のお役立ちコラム〜心理士の役割と貢献〜

皆さんこんにちは!ほっとmamaで働く公認心理師のKです。
今回はシリーズ第3!「心理士の役割と貢献」について詳しく解説していきます!
臨床心理士や公認心理師など、心理士の資格はいくつかあり、福祉や教育、医療など幅広い分野で活躍をしています。今回は、その心理士が、放課後デイサービスの現場でどのような役割を担っているのかについて、お話したいと思います。
◇公認心理師の役割と放課後等デイサービスでの貢献
子どもや保護者の悩みや困りごとをきくことや、放デイでの子どもの様子(学習や遊びなど)を観察し、子どもの現状を把握すること、支援を考える際に専門的な視点から助言をすることなど、心理士に求められるものは多く、質の高いものが求められるようになってきました。心理学を学んできた専門家として、その知識や経験をいかし、子どもや保護者が安心できるよう支援や助言をすること、課題や問題が解決・解消するよう関わることが心理士が提供できるサービスだと思います。
◇放課後等デイサービスでの心理的支援の重要性
知的障害や発達障害、発達特性のある子どもは、定型発達の子に比べて、感覚の発達や心理的な発達がゆっくりです。そのため感覚が過敏(鈍麻)なことや、感情のコントロールが十分にできないことなどがあります。日常生活や集団の中で、適応しきれないこともあるかもしれません。問題行動や心配な様子がみられたとき、その原因や要因を探り、対策や支援方法を考えることはとても重要です。心理士はその知識や経験から、子どもの課題を把握し、解決や解消に向けて対策や支援を考えます。子どもが安心して日常生活を送ることや、自信を失わないこと(自信をもつこと)ができるように支援することが大切だと思っています。
◇サービス提供における心理士のスキルと方法
コミュニケーションが苦手、気持ちの切り替えが苦手など、課題を持つ子への支援を考え、問題や課題の解決・解消に向けて取り組むことは、心理士の役割の一つです。また、障害や特性を持つ子の家族へのサポートをすることも大切な仕事です。
◆アセスメント
「その子の発達はどの程度なのか」「得意なこと・苦手なことはどんなことか」「今の課題はどこにあり、どんな支援を必要としているのか」など、日頃の生活(学習や遊びなど)の様子をもとに現状を把握し、支援について検討をしています。
◆子どもへの支援とアプローチ
子どもが興味のあることや好きなことを認め、それをもとに支援を検討します。苦手なことでも「これだったらできるかも?」と興味を持ってくれることや、「やってみたらできた!」と自信や安心につながる支援を考えます。時には子どもと一緒に取り組み、時には保護者へのアドバイスとして提案することもあります。
◆家族・保護者への支援
発達特性や、障害のある子をもつ保護者の中には、育児のしにくさから「親としての自信」を失くしている方や、周りからのなにげないことばに傷ついている方が多くいます。また、「周りに迷惑をかけてはいけない」「『普通』に育てなくといけない」と必死になっている方もたくさんいます。心理士は、そのような保護者の気持ちに寄り添い、負担を軽減するためにどうしたら良いかを一緒に考える存在です。
◆関係機関との連携
学校や自治体(福祉課や保健センターなど)、医療機関と子どもの課題や障害について情報共有することや、理解を求めるための働きかけをします。子どもが安心して社会生活(集団生活)を送るきっかけを作ることや、家族と関係機関をつなぐお手伝いをしています。
その他にもいろいろありますが、これをきっかけに心理職の仕事に興味を持っていただけたらうれしいです。
公認心理師のお役立ちコラム〜放課後等デイサービスの役割〜

皆さんこんにちは!ほっとmamaで働く公認心理師のKです。
今回はシリーズ第2弾!「放課後等デイサービスの役割」について詳しく解説していきます!
◆障がいを持つ子どもへの放課後等デイサービスの提供方法
放課後等デイサービスでは、専門職職員が在籍していることがあります。そして、専門職による子どもの見立てなどから、子ども一人一人にあった支援を提供することができます。
理学療法士
体の動かし方について、評価やリハビリをしてくれます。起きる、立つ、歩く、座る、跳ねるなど、日常生活における動作の改善をはかり、訓練してくれます。
作業療法士
日常生活の中で何気なく行っている「作業」の評価やリハビリをしてくれます。物をつまむ、はさみを使う、箸を持つなど、日常生活で欠かせない動作をスムーズに行えるよう、遊びを通して訓練をしてくれます。
言語聴覚士
「ことば」や「聴こえ」、「飲み込み」の評価やリハビリをしてくれます。「ことば」だけでなく、食べ物の飲み込み方など、舌の使い方も訓練してくれます。
心理士(臨床心理士、公認心理師)
生育歴や日常生活の様子など、様々な情報をもとにアセスメントを行い、より良い支援について考えてくれます。会話ができない子どもの心の問題やストレスも、遊びを通してケアしてくれます。
◆放課後等デイサービスが子どもの発達に与える影響
発達の遅れや特性のある子どもは、日常生活や集団生活の中で、ストレスや疲れを感じやすい傾向があります。放課後等デイサービスでは、専門職による関わりによって、心身の発達を促すことや、子どものストレスや不安を軽減することができます。それだけではなく、子どもが安心して、ちょっと一息つける場は、日々の学習や経験を定着させる基盤となります。家庭以外の拠点として、子どもが安心してすごせる場があることは、基盤づくりにも大いに役立ち、新しいことに挑戦する意欲につながっていくでしょう。
◆家族との連携を強化するための放課後等デイサービス
毎日子どもと接していても、その成長に気づきにくいことや、支援が必要なことを理解していても、家庭でなかなかサポートしてあげられないことなどがあります。ちょっと気になることがあっても、なかなか相談できないということもあるかもしれません。放課後等デイサービスを利用している子どもだけでなく、その家族も支えるのが仕事です。そのため、定期的な面談を行い、様子や情報を共有していますが、それ以外にも、電話連絡や送迎時などの会話も大切な時間だと考えています。困ったときに頼れる場所は、子どもだけでなく、家族にも必要です。子どもとその家族が、安心して、落ち着いた生活できるよう、連携をはかることが大切なのだと思います。
公認心理師のお役立ちコラム〜放課後等デイサービスとは〜

皆さんこんにちは!ほっとmamaで働く公認心理師のKです。
今回新たな取り組みとして、放課後等デイサービスについてや、障がいを持つお子様についての情報を公認心理士目線で発信していきたいと思います!
初めてのコラムは「放課後等デイサービスとは何か?」についてです!
是非最後まで読んでいただけたら嬉しいです。
シリーズ1:放課後等デイサービスとは何か?
◆放課後等デイサービスの基本と概要
放課後等デイサービスは、主に小・中学生を対象とした放課後や休日に提供される社会福祉サービスの一種です。子どもの発達段階や障害特性に応じた対応や、自立に向けた支援を行っています。活動内容は事業所や施設によって異なりますが、学習支援や社会性・人間関係を学ぶための遊び、送迎サービスなどがあげられます。障害や特性のある子どもの学童というイメージです。
◆放課後等デイサービスのメリットと利点
学校で学習をし、放課後は友だちと遊び、家庭では家族と過ごすという一日のサイクルの中で、放課後デイサービスは、家庭と学校のバランスを助ける役割を担っています。放課後という貴重な時間を放課後デイサービスで過ごすということは、子どもたちの総合的な発達を促す機会でもあります。
例えば・・・
・社会的なスキルの向上
異年齢で、市町村や校区の違う児童・生徒同士が遊びなどを通して交流することができます。社会的なスキルやコミュニケーションスキルが獲得、向上できる可能性があります。
・遊びや活動の提供
遊びや活動を通して、子ども自身がさまざまな経験を積むことができます。日ごろの生活だけでは体験できない活動を通して、子どもたちの興味を広げ、特技や才能を見つけるサポートをしています。
・学習支援
宿題や学習に対するサポートを提供。学習の理解を深めるだけでなく、学習への取り組み自体に工夫をし、アプローチをすることがあります。
・保護者への支援
保護者が安心して仕事に従事できるようサポートするだけでなく、保護者が感じている不安や困り感、気になっている様子を相談することができます。
◆子どもと家族にとっての放課後等デイサービスの重要性
障害や特性のあるお子さんは、定型発達のお子さんに比べて時間のかかることや、個別の配慮が必要なことが多くあります。発達段階や障害の程度によっては、保護者の負担や子どもの困り感が大きくなってしまうこともあります。放課後デイサービスでは、保護者が安心して仕事ができるよう支援をするだけでなく、子どもたち一人一人の障害や特性に向き合い、支援をすることで、子どものからだと心の成長や発達を促しています。